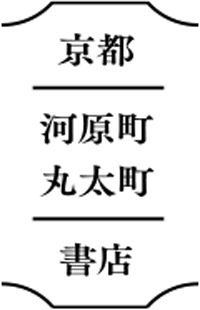富士宮やきそばとわたし
甲斐みのりの焼きそば道楽
文:甲斐みのり写真:村上誠

気が置けない親しい人ができると最初に贈りものに選ぶのは、たいてい焼きそばだ。誰かが初めて我が家にやってくるとき、まずふるまうのも焼きそばと決めている。焼きそばは私にとって幼い頃から慣れ親しんだ故郷の味。大がつく好物でもある。私の焼きそば好きは、“焼いた麺”ならばなんでも好意的に思えるほど大様に育まれてきたけれど、繰り返し取り寄せているのは「富士宮やきそば」だけ。
富士山の伏流水を使いながらも、蒸した麺を他地域の焼きそば麺のように湯通しせず急速に冷やして表面を油でコーティングするため、水分量が少なく独自のコシが生まれるむし麺。辛口のウスターソース。イワシの削り節と青のりをまぜた「だし粉」。「焼そばの友」と名付けられた豚の背脂からラードを搾り取ったあとに残る「肉かす」。富士宮やきそばを作るのに必要な材料が一式揃ったセットを、地元・富士宮市の製麺所〈マルモ食品工業〉から手配する。

もともと富士宮やきそばは、マルモ食品工業の創業者が、戦時中に東南アジアで食べたビーフンの食感を再現しようと麺を作り、製系業が盛んだった富士宮で女工たちの日常食として、小麦粉生地にキャベツを入れてソースで味付けした「洋食」と呼ばれる具なしお好み焼きとともに溶け込んでいった郷土食。自分で作るときも本来の形に近づけて、合わせる具材はキャベツ・豚肉・紅しょうがのみ。市内に150軒近くある富士宮やきそばを食べられる店では、イカ、タコ、エビ、桜エビ、ホルモン、たまごなどトッピングを選べるが、できるだけシンプルである方が、もちもちとした麺の歯ごたえと肉カスの旨みが相まって生まれる、特徴的な風味が強調される。

私が富士山麓ののどかなまち富士宮で過ごしたのは18歳まで。大阪の大学に進学した頃は、出身地を聞かれると、「静岡県で、富士市の隣の……」と、どうにもぼやけた返事をしていた。隣接する富士市には東海道新幹線の新富士駅や旧東海道の吉原宿などがあるけれど、当時は富士宮と言ったところで、文化圏が異なる関西で認識してもらえるはずもなかった。ところが今は日本中どこへ行っても、「ああ、焼きそばのまちね」と話が早い。“B級グルメ”という言葉は好きではないが、2006年から始まったB級グルメの人気を決める「B-1グランプリ」で、「富士宮やきそば」は第1回目と第2回目、2年連続でグランプリを受賞している。“ご当地グルメ”ブームの火付け役として、頻繁にマスコミに取り上げられるようになり、地元がテレビに映るたび、誇らしいような、照れくさいような、不思議な気持ちで眺めていた。

小学生時代はよく、放課後や午前中で授業が終わる土曜日に、幼馴染と連れ立って近所の駄菓子屋に出かけた。富士宮の多くのの駄菓子屋には、大きな鉄板がのった焼き台があり、当時は250円から300円くらいで、お好み焼きや焼きそばを食べることができた。だいたい店主は、小学生から年配者までが「おばちゃん」と呼んで親しむ、地域のお母さん的存在。小学生がおやつ代わりに、2~3人で一人前のお好み焼きや焼きそばを注文しても、嫌な顔ひとつせずにこやかに焼いてくれた。ときどき祖母にお小遣いをもらっては、品書きの中で一番高い、お好み焼きと焼きそばを合わせた「しぐれ焼き」を食べるのを楽しみにしていた。しぐれ焼きは普通に焼きそばを作るより麺や生地が鉄板で熱される時間が長いからか、ところどころにカリッと焦げて固くなった麺が混ざる。子どもながらに、そのカリッにこの上ない幸せを感じていたから、今も家で焼きそばを作るとき、麺の一部がカリカリするように、あえて焼き時間を多くとる。
好きなものを、好きな人と、好ましい環境で味わえば、なんだっておいしいと感じる、グルメでも食通でもない私だが、これからただ「好き」という気持ちだけで、焼きそばや、“焼いた麺”について綴っていこうと思う。食べることが好きで、焼きそばが好きで、まちや旅が好きで……。ああ、今さらだけれどこれは、“焼きそばについて”というよりも、“好きなものをひたすら追いかける”ことや、“好きなものに包まれる多幸”の記録になる気がしてきた。