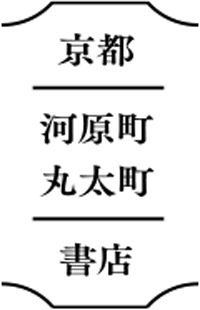葉隠(前編)
和田夏十の言葉
確かなもののない時代に、小さな確かなものを無理無体に造り上げ、それを確かなものであらせ続けるために死力を尽くすというのは、いじましい。
『和田夏十の本』「(『葉隠』上を読み終わった)」より

子どもの頃、祖父には本当によく叱られた。
私の母方の祖父、つまり母の父親は大正10年の生まれだ。幼少時代は瀬戸内の島で育って戦争で徴兵され、終戦後、鳥取に移り住んでクリーニング店を始めた。家族親族と、数人の職人で切り盛りする小さな店だ。祖父本人はカタカナ語を使わず、自分の仕事を「洗濯屋」と呼んでいた。
洗濯屋の工場はいろいろな音がした。大型の洗濯機が回る「ダダダダダダダダ」という地響きのような音。人体型のスチームアイロンから上がる「プシューッ」という蒸気の音。洗濯物を積んだ竹製のカゴを引きずる「ガサササーッ」という音。客が来ると鳴る「ピロロロロン」というベルの音。そして、洗濯物のポケットの掃除をする親戚のおばさんたちのおしゃべり声。
結婚後も実家で働く母の仕事の邪魔をしながら、私はここで育った。
洗濯屋の繁忙期は夏だ。衣替えで冬物が一斉にクリーニングに出され、それをひと夏かけて一家総出で片付ける。大型化したクリーニング会社が主流となった今からすると考えられないかもしれないが、当時、個人商店の洗濯屋はそんなリズムで仕事をしていた。
夏場、冬着の洗濯物は工場から溢れかえり、工場の2階にある祖父たちの住まいまで侵食した。
こんもりと積まれた、大人の背ほどもある洗濯物の山がいくつもいくつも出来て、一つ一つに埃よけの白いさらしがかけられていた。その姿はまるで、雪国のかまくら祭りのようだった。
これが子どもだった私の格好の遊び場になった。よじのぼったり、踏みつけたり、すべり台のようにして遊んだり。大人たちは、少々のことは大目に見てくれたが、行き過ぎると祖父の怒声が飛んできた。
「コラーッ!」
両手にこぶしを握り、目を三角にして力の限り怒鳴る。それが心底恐ろしかった。「いい加減にせんか!」という追い討ちのひと言には、子どもながら自分が情けない思いがした。商売は遊びではない。そんな社会の決まりの重さを、雷が落ちるような祖父の怒鳴り声で思い知った。祖父にとって念願の初孫だった私は、普段これ以上ないほど甘やかされていた。それだけに、ここぞというときの祖父の雷は堪えた。
しかしときどき、小さな子どもには理解に苦しむものもあった。
祖父が習い事の迎えに来てくれた際、授業が終わってひとまずトイレに行った私は、出口から吐き出される子どもの一群から少し遅れて教室の外に出た。
祖父の姿を見つけて駆け寄ると、出てくるのが遅くなった理由を訊ねられたので、私は何とはなしに事情を話した。すると突然、祖父の雷が落ちた。「よその便所を借りるなどけしからん。用は家で済ませなさい」というお叱りだった。その場では「ごめんなさい」と謝ったものの、私には釈然としないものが残った。家に帰ってそのことを母に話すと、母も理由は「わからん」と首をひねっていた。
新しくできた友だちが、洗濯屋に遊びに来たことがあった。遊び場でもあった工場の中を私が案内していると、そこにも祖父の雷が落ちた。「忠臣蔵を知らないのか。討ち入りにでも入られたらどうするのか」。チョンマゲ時代の話など、はるか遠い昔のことだと思っていた私は、ひたすらぽかんとして謝ることもできなかった。
しばらくしても、私はその雷のことが心に引っかかっていた。
もしかして、祖父が生まれ育った昔には、今と違う物の道理があったのではないか。「ジェネレーションギャップ」という言葉はまだ知らなかったが、次第に「今と昔の間にある時代の溝」に興味を持つようになった。
和田夏十は、私の祖父のひとつ上の大正9年、つまり1920年の生まれだ。『和田夏十の本』にはこういう記述がある。
「私が小学生の頃、祖父が亡くなった機会だったかと思いますが、父が分家しました。父は二男だったからでしょう。いわゆる昭和の一ケタの時代でしたが、その頃学校へ提出する書類や何かでも苗字の上に士族とか平民とかを記入する欄があったんですね。そこへ、今まで士族と書いていたのに、平民と書かなければならなくなりました。分家したからだというのです。私は非常に残念に思いました。」
これを初めて読んだとき、「士族」や「平民」という、私が歴史の教科書でしか触れたことのなかった言葉の登場に驚いた。さらに、「士族」の身分にこだわる様子は、市川崑監督作品で見せる現代的な作風からは意外に思えた。
(後編に続く)