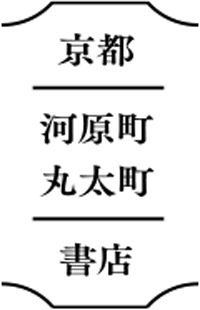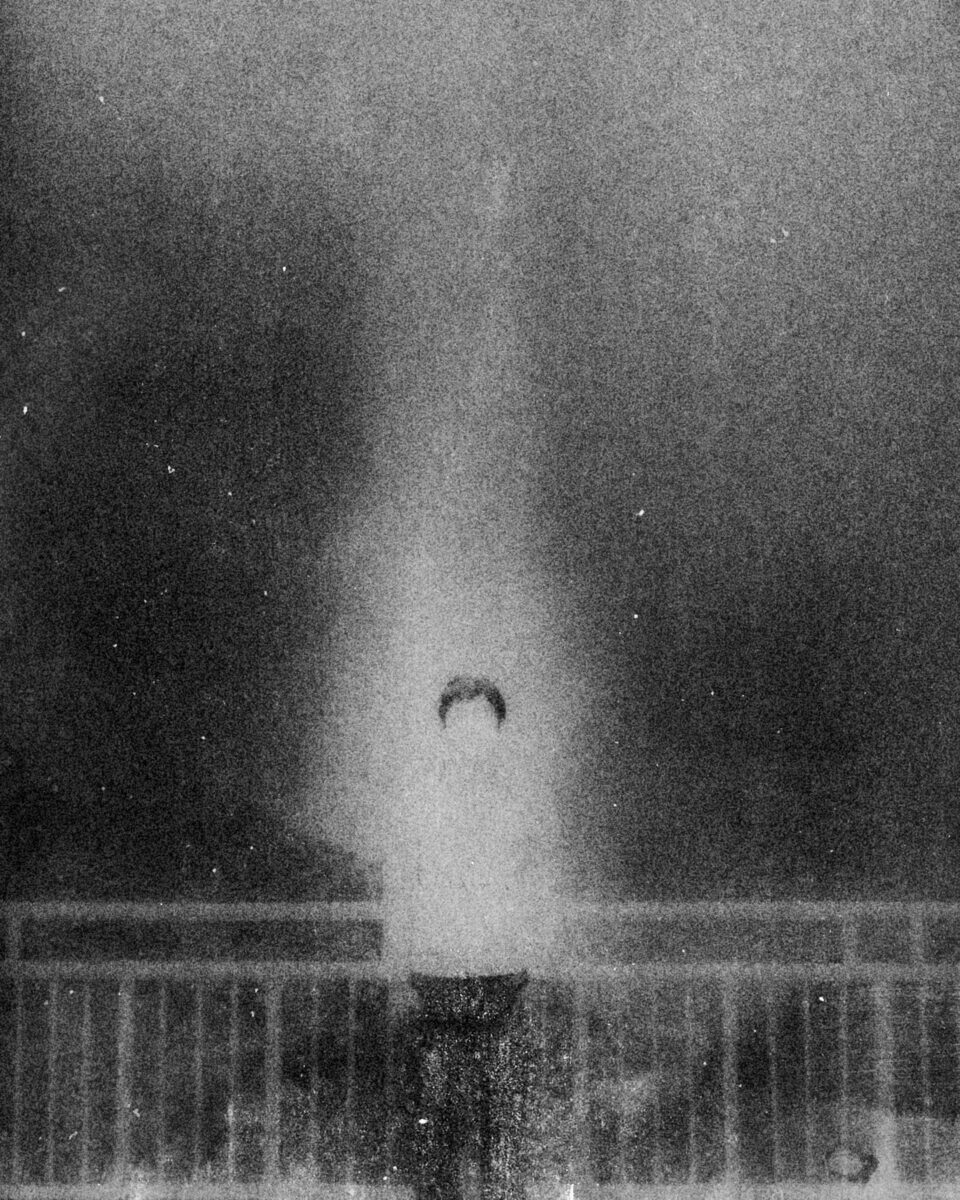
木村肇 「嘘の家族」刊行記念トークイベント 後編
木村肇 「嘘の家族」刊行記念トークイベント
出演吉田亮人出演木村肇
(前編より続き)
吉田:ほんと知らなかったことがいっぱいありました。そして話を聞いて僕は、この作品は肇君にとって作らなくてはいけないものだったんだなということがすごくわかったんです。『Snowflakes Dog Man』を作ったこともそうだし、家族に特化した作品を作ったというのが、実は自分のなかのコンプレックスや乗り越えられなかったものを、写真を撮って何度も編集して手を動かすことによって思考を深め、乗り越えていく。そんな大事なプロセスだったんじゃないかなと思います。その乗り越えらなかったものってなんだったんでしょうね。
木村:僕が家族をテーマに作品を作りたいと思えたのはなぜか。僕は「自分の家族はこうなんだよ」と周囲に嘘をついてたと言いましたけど、20歳過ぎるくらいまでずっとだったんです。母は亡くなっているのにまだ生きてるとか言っていました。距離の近い友人はそれが嘘ってわかっています。逆に大学で少し会うだけの友だちには言う必要がないというか、言うことで空気を悪くするのも違うなと思って言いませんでした。母が生きていると思い込んでいたのか、消化しきれなかったのか、もしくは嘘をつくことでどうにか外側の人と繋がっていたかったのか。そういったことじゃないかと思っています。でもお酒飲んだりすると本性が出てくるというか話に整合性がなくなってきて、話しているうちに「この前生きてるって言ってなかったけ?」と言われることがあるんです。偽りの家族像を言い続けるってかなりしんどいんですよね。ちょっとしたことでほころびが出始めて隠し通せなくなります。

吉田:だから嘘をつくためにまた嘘を重ねて、整合性をとるために複雑な話を作らないといけないという。しかも誰にこの話したんだっけっていうのも覚えていないんですよね。そこであるときから嘘をつき続けることが大きな心理的負担になってきた。
木村:おっしゃる通りです。大学を休学してバックパッカーみたいなことをやっていたのも刹那的な関係を求めていたからかもしれないなと。その場限りの関係だったらいくら嘘をつこうがバレないじゃないですか。だから深い関係になる前にそこから逃げるしかない。自分の嘘をつき通す手腕がないんですね。そのことに段々疲れてきました。
今回のタイトル『嘘の家族』もそれが理由で、ここで描かれている家族というのは、例えば写真を始めるより前に思い描いていた偽りの家族像です。もしかしたら小学生のころに母親の年齢や家族が喧嘩していることを言えればそうはなっていなかったかもしれない。嘘をつくってことはこの場合見栄を張ることでもあると思うんですけど、長い間続いてしまった。
吉田:なかなか乗り越えられないし本当のことを言えばいいのに言えない。かといって嘘をつき続けると実生活に障害が出てくる。
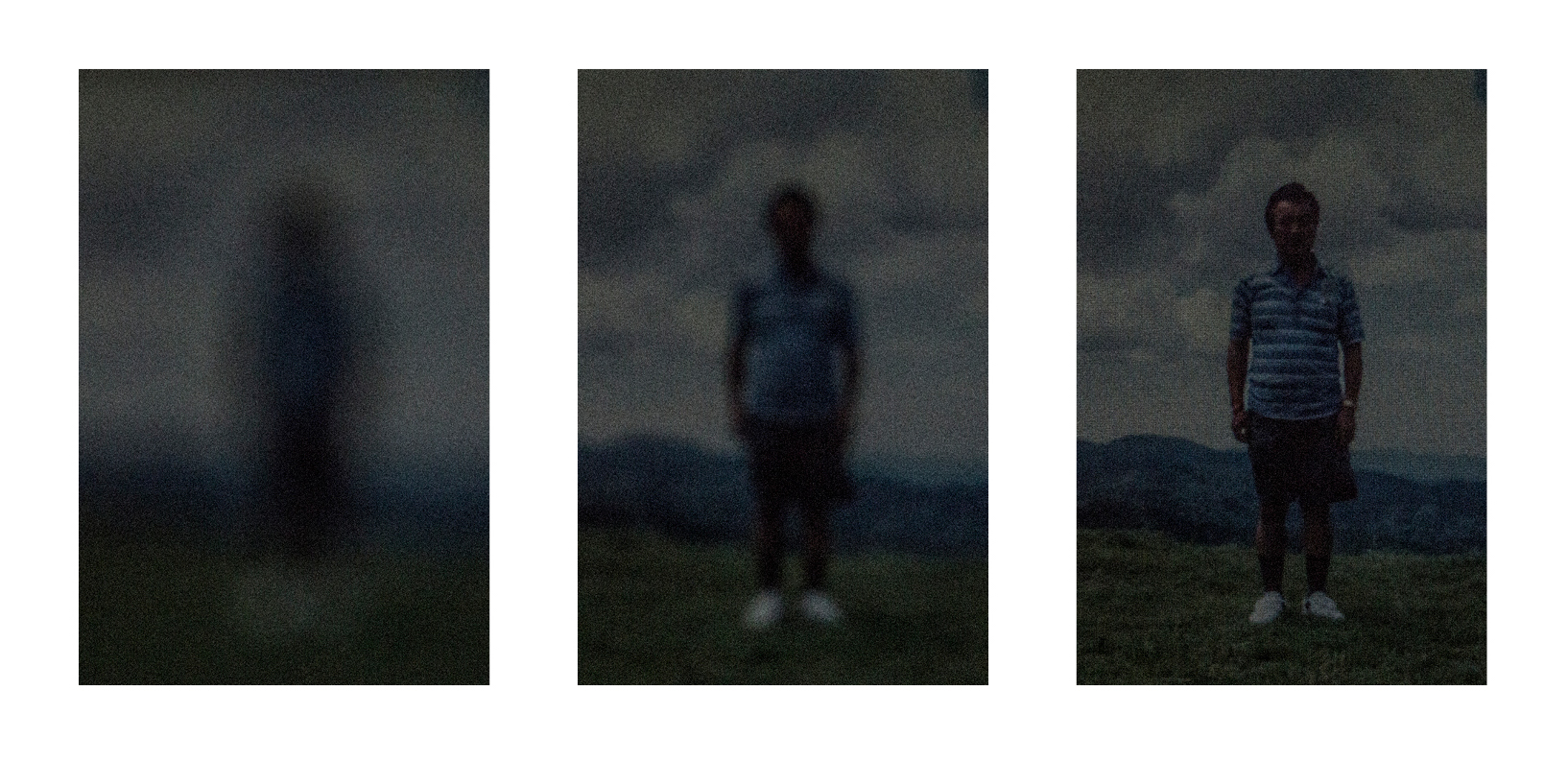
木村:話は前後しますが、僕は小学校から大学、社会人までサッカーをやっていました。でもそれ以外の時間は本当に居心地がよくなかったんです。良い学校から良い会社に入るっていうのを植え付けられていたから、クラスで自分がどう振舞ったらいいのかっていうも考えていて、自分はマジョリティでいたかった。偏差値で言えば真ん中のところにいたかった。そうすれば誰からも何も言われないからです。でも16歳のときに母が亡くなってからグルっと変わってしまった。周りは両親がいるけれども、自分は母親がいなくなってしまった。それを受け入れてしまうと自分が偏差値50という真ん中ではいられなくなります。だから担任の先生にも母が亡くなったことはクラスに言わないでくれと。でも翌日に学校に行ったら友だちがすっごい気を遣ってくれていて、よそよそしい感じでした。だから絶対先生が言ったんだと。そのときから色んなことが信用できなくなったというか。友だちの考えや振舞いにいちいち疑いを持つようになりました。でもサッカーをやっているときはそんなこと考える暇がないから救いだったんです。とにかく世の中で起こることをいちいち疑うようになってしまって、それは母が亡くなった経緯にも関係があるような気がします。見つかったときにはステージ4の肺がんで亡くなったのですが、でも直前に行ったクリニックでは風邪って言われていたんです。現代医療に絶対の信頼を置いていたのに裏切られた気がして、そこからも色んなことを信じられなくなります。だから違う人物像を自分で作らないと自我が保てないような状態だったのかもしれないです。
これまで自分がやってきた作品というのは表面的なところだけを見せていました。それも作品ではあるのですが、今回吉田さんに感謝したいのはテキストベースの見せ方を提案してくれたことです。なかなかビジュアルでは表現しきれないような、「自分がなんで作品を作っているのか」ということを掘り下げて出版してくださって感謝しています。
吉田:僕もとても興味深くお話を聞かせてもらえて感謝しています。僕は正直『Snowflakes Dog Man』が本の形態としてもそうだし、写真の表現もそうだし、完璧に近いと思っています。だからこそその作品を膨らませるかたちでお父さんについてのお話を聞けたらいいなというのは最初から思っていました。だけど、去年の10月に肇君の家に行って3、4時間、ごはんやお酒を飲みながら話を聞いてたところ、驚くようなことがたくさんありました。ある程度の年齢になったのにお母さんが亡くなったことを言えていないとか。『Snowflakes Dog Man』発表時にはお父さんにまつわる本だというのは言っていなかったんですよね。

木村:そうです。さっきも言ったように東京で出会った一人暮らしの老人と同じ年代というのもあるし、ずっと会っていなかったというのもあって、父親でありながら他人みたいだったんですね。そういう観点で撮った方がいいんじゃないかと思っていたんですけど、それが精いっぱいだったのかもしれません。
吉田:メディアでも敢えて「男性」という言葉を使っていましたよね。だから他人として撮っていたってことだと思うんですけど、その話を聞いたときも衝撃を受けて益々興味深く思いました。ここで急にさっきのマタギの話に戻りますが、嘘をついていたり、なかなか言えないことがあったりというふうに過ごしてきたけれども、写真を通して関係性を築いて、何度も通って、彼らには本当のことを話すことができたんですよね。
木村:そうなんです。足がけ7年通って本当のことを話すことが出来る人たちだった思ったんですね。飾り気もないし、熊を仕留めてその場で分解してその場で食べるみたいなことを一緒にしたりしましたけど、そのなかで「なんかもう嘘なんかつかなくていいや」って。だから両親がいないてってことをふつうに話してみたらすっごい楽になったんです。なんでいままで言わなかったんだろうってくらい。自分が何かを表現するときに嘘をつくことは足かせにすらなるんじゃないか、早くやめたほうがいいなってことに気づいたんです。
吉田:たしかに本のなかでも写真作品を作るうえでの足かせになるという話をしていましたね。つまり嘘をついて自分に重りをかけて撮影するのは自分にとってかなり不利なのではないかと。
木村:さっきも言ったように表現に先立って関係性を作ることの重要性がありますが、そのなかで自分が偽りの家族のことを話すっていうのは矛盾しているんですよ。自分の表現に対しても嘘をついているような感じがしてきました。それをやり続けると破綻するなと。じゃあそれを第三者に言うためにはどうしたらいいんだということで、家族を撮ると。この前に作った『In search of lost memories』は自分の記憶に関するリサーチでもあるんですけど、家族の記憶を遮断していた時期に臨床心理士の人にずっと診てもらっていたことを描いた本です。それは作品を見てもらって意見をもらうというコミュニケーションを第三者ととることで、自分の母親が亡くなったこと、自分の家族はこうだったんだということを言う機会になると。だから自分のためというか。自己セラピーみたいな。また、表現を正すという意味でも家族をテーマにした作品を作ることが必要だったんだなと、今回のこの本を出させてもらってより強く思いました。

『Snowflakes Dog Man』を刊行したときも本を出すことで自分の家族を知ってもらう、そして自分が嘘をつかないでいられる機会を自分で作るってことなんだなと思っていました。でもそこから時間を置いてまた今回の作品で改めて文面にしてもらったことで自分のなかでの楔になりました。逃げも隠れもできない。嘘をつかないなんて一般的には当たり前のことです。でも、僕にとっては表現や自分のメンタルを保つために、嘘をつかないでいることが重要なんです。
吉田:インタビューのときもこうやってあけっぴろげに話をしてくれました。いままで自分の家族のことに蓋をしてきたとは思えないくらいだったし、全部書いてくれて良いって言ってくれたことも印象的でした。信頼を置いてくれていたからかはわかりませんが……
木村:信頼していたのはありますよ。似たようなテーマでも作品を撮られていて、そのあたりのことがなんとなくビジュアルランゲージとしてもわかる人たちだとわかっていたからやろうと思ったんじゃないかな。
吉田:だから萌さんともよく話していたんですよ。だってこっちから「ここ、こうしたいんだけどどう?」って聞くと「どうぞ」って、ほんとに思ってるのかなって。
木村:さすがに母親のからあげのところはなしだと思いましたよ。家族のことを思い出すときに小4、5くらいに鴨川シーワールドに行った光景があるんですよ。そこでお弁当を食べようってときに僕のからあげを妹が盗ったんです。すごく腹が立って妹からからあげを取り返したら、母親にはたかれて、からあげがコロコロと転がっていきました。それを聞いて、「母と妹の鴨川シーワールドのからあげの記憶」というタイトルにしようって言われたんですよ。それはないだろうと(笑)。
吉田:もちろん冗談で言ったんですけど、シャチとかサメとかじゃなくて、からあげがコロコロ転がっていた光景がイメージとして残っているというのは面白いなと。
それは良いとしてこの本は誠光社を皮切りに色んなところに展開できればと思っていますが、やっぱり海外からすごい注文が来るんですよ。僕に直接DMが来ることもあります。マタギの写真集も持っている方とかから、すごい長い文面でビジュアルとしてひじょうに優れていると書いてきたり。いいねだけ押しましたけど(笑)。だから海外の方にしっかり届けたいと思いました。その一方でお話を聞いている過程で思ったのは、特殊な話に聞こえるんだけど自分の経験を思い出したときにも「なんかわかるな」って。だから肇君の家族の話をきっかけに読者それぞれの家族の関係性を考えたり、コミットしていくような普遍的な話なんじゃないかな。
木村:僕がマタギを撮っているときってYouTubeもインスタもなかったけど最近は何かしらペルソナを演じるような機会がある。でも、ずっとその嘘をつき通すことなんてありえないじゃないですか。会社にいるときと友だちと飲んでいるときとで振る舞いは違うじゃないですか。なのに、なにかを掛け違えて、それを本当の自分だと思って演じ続けるケースもある。僕の場合は精神的に未熟だった小学校低学年くらいのときからそれをし続けてきた。いまでは変なことだってわかりますけど、当時はある意味で自然だったのかもしれません。昨今の、SNSが当たり前になった社会で起きていることに近いようにも思えます。
吉田:家族の話も興味深いのですが、もうひとつ、写真作家としての表現の仕方が巧みだなといつもながら思いましたね。今回の本のなかにも作品制作にまつわる話が書いてありますが、ひとりの写真作家として「なるほど」と思うことも多かったし、写真に対するコミットの仕方や思考の在り方がかなり勉強になります。ちなみに今取り組んでいる作品や今後の展望ってのはありますか?
木村:けっこうあるんですけど、ずっと長く取り組んでいるのは東京大空襲のプロジェクトです。2019年からいままでやっているんですけど、東京大空襲をモチーフにして記憶が変わっていくというちょっと不思議なプロジェクトです。空襲を3つにわけて分析していて、ひとつは町、ふたつめは体験者。東京大空襲の戦災樹木というのがあって、それを体験者の代わりに撮っていました。でもその樹について全然知られていないんですよね。広島や長崎の原爆樹木とは扱われ方が違っていて、樹がアウトサイドから見た記憶の集合体だとしたら東京大空襲がぜんぜん認知されていないということがわかりました。その理由を、それを取り巻く環境、町の変遷、木にまつわる空襲体験者の3つから考えてみるというプロジェクトです。記憶が町の変遷、歩み方の違いでぜんぜん変わってしまうという、環境と記憶に関することをずっとリサーチしています。

これも家族を通して記憶それ自体に関心が動いたことが大きくて、記憶って何なのかなって。もともとはソリッドなものというイメージがありましたが、本当はすごく流動的で形がなくて、自分の環境や健康状態が変わるだけで同じく変わってしまうような有象無象なんじゃないかと思うようになりました。それを家族というテーマでやっていましたが、今度は空襲体験というよりジェネラルな題材で構築しようとしていて、アニメーション、映像、写真とマルチメディア的な手法でアプローチしています。
吉田:じゃあ発表の形はもちろん本の形態も取りうるし、アニメーションや映像を見せたりと展開の仕方は色々あるということですね。
木村:そうですね。もちろん本は作りたいと思っていますが、展示の在り方は色んな選択肢があってよいと思っています。
吉田:でも肇君はどの作品でも、記憶や忘れ去られようとしているものに行き着きますよね。そういうところに鉱脈を感じているのかなって。
木村:主観的に「絶対にこれはこうだ」と覚えていることがありますよね。家族のある日の思い出を妹と確認し合ったときに、僕はすごく自信満々で「どこどこにどうやって行って」と話をしたら妹が違うと言うんです。それでちゃんと調べたら妹が合っていたんです。だから記憶がどこかですり替わっていたんですけど、それから急に自分の記憶に自信が持てなくなってきました。記憶ってなんなんだろうって。その記憶が別のものとして記憶されていたことにも気づいていなかったんだから。歴史もそうで、自分たちが学んできたことは本当は違うんじゃないかとか。だからその記憶を視覚的に表現するにはどうしたらいいだろうとか考えるようになりました。
吉田:それが今日一番最初に話した「写真を残したい」という発言は、そういうところから出た発言だという気もします。記憶は改ざんされたり変化していくものだけど、写真は一枚の絵として残るじゃないですか。でも100年、200年くらいのスパンで見るとその写真自体にまつわる情報が漂白されていくこともあると思うんです。この人って誰?みたいな。撮った直後はその人たちも生きていたりとか、風景もそこにあるんだけど、10年でも写っているものの意味合いが変わったり、漂白されていく。そういう意味で写真でもすべてを残すことができるのかどうか。絵としては残るけど、記憶や情報としてはどうなんだろうと。それらがいかに曖昧で脆いものであるかっていうか。それに抗うかのように「残したい」と若き肇君が言っていて、僕も同じように思いました。
木村:僕が紙媒体にこだわっているのは記憶に楔を打って所有できるからというか。それは紙媒体の特権だと思っています。
吉田:ほんとにそうです。京都に800年くらい続いているあるお家があって色んな貴重な資料をご自身の邸宅のなかに持っています。僕はいま奇跡的にそこに行って写真を撮らせてもらっていますが、つい最近新しい資料を見つけて調べたら、古今和歌集の原本だったみたいなんですよ。800年前に書かれた紙の文書が残っていると。そこのご主人が言っていたのは「デジタル写真に移り変わっているけど電気がなくなったらどうすんねん。後世に伝えられへん」と。だから全部紙に印刷して残すと。しかも保管の仕方は美術館、博物館レベルの設備を整えるのではなく、ただの蔵。蔵が最強なんだそうです。とにかく紙媒体が時代を越えて残っていくというのをまざまざと証明してくれるようなお家が近くにあるという話で、だから益々こういうものに自分の写真とか、自分がほれ込んだ作家さんの写真を閉じ込めて残したいと思っています。
(終)