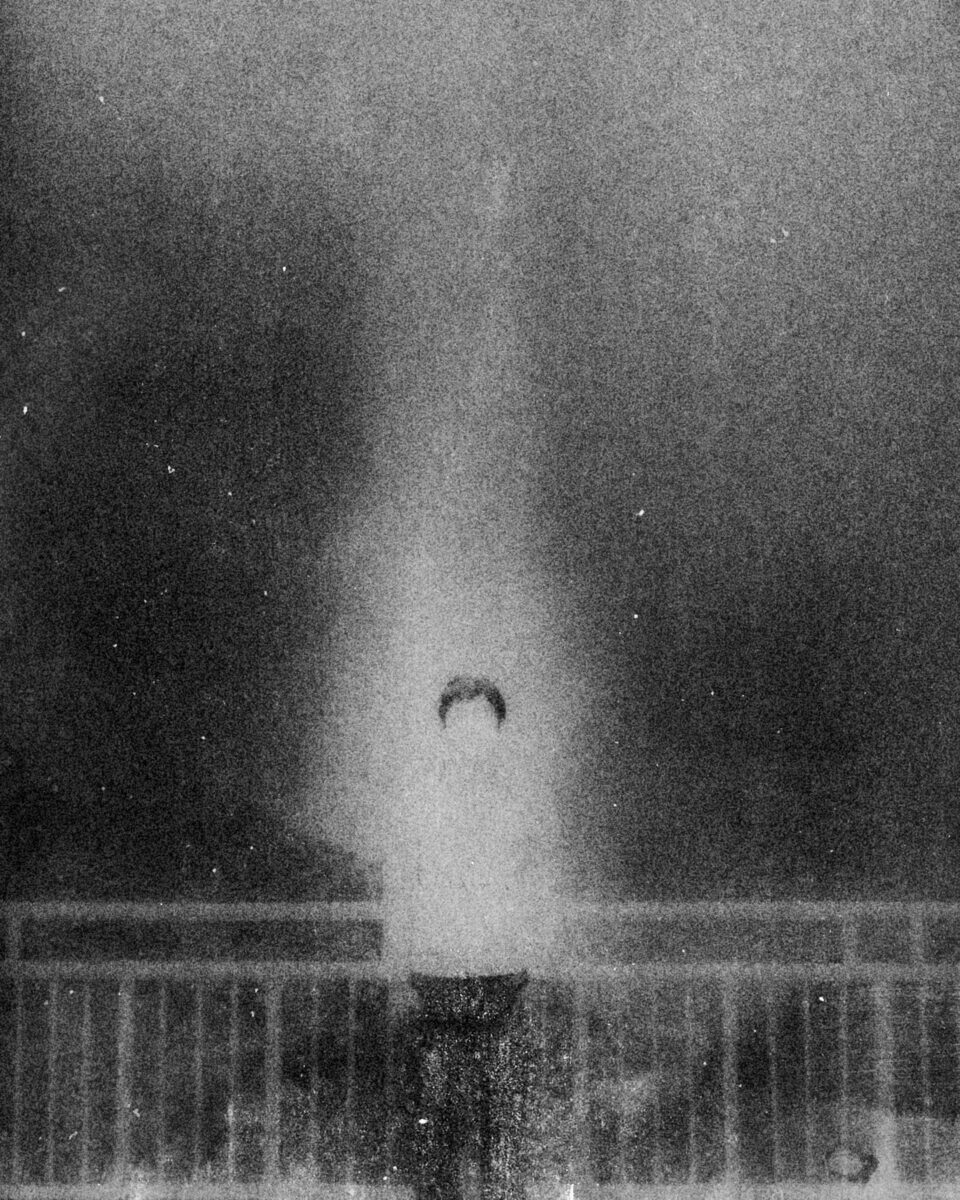
木村肇 「嘘の家族」刊行記念トークイベント 前編
木村肇 「嘘の家族」刊行記念トークイベント
出演吉田亮人出演木村肇

(文字起こし:石川宝)
吉田:three booksは、東京在住のビジュアルアーティストの鈴木萌さんと僕とで、写真をメインにした本を作ろうと、昨年4月に立ち上げた出版社です。一冊目として僕の本を出した後、次はどうしようということでシリーズものの企画を立ち上げました。「声プロジェクト」と銘打って、作品とその作家さんへのインタビューを一冊にまとめた、半分写真集で半分書籍のような本を作ろうと。その第一弾として誰がいいだろうと話していたところ、白羽の矢が立ったのが木村肇さんでした。
木村さんは千葉に拠点を置きながら制作されていて、とりわけ本という形式でのアウトプットを精力的になされています。僕の印象では日本よりもヨーロッパやアジアなど、海外での評価が高く、向こうの出版社から写真集を何冊も刊行されていますし、展示やフォトフェスティバルにも招待されています。
僕はこの『嘘の家族』という作品を見て思ったのは、とてもエモーショナルだし、写真表現として素晴らしい構成をされているということ。でも彼の家族に関する話はあまり知りませんでした。今回インタビューを敢行することで、たぶんメディアとかでもあまり言っていない秘められていた家族の話を知ることができました。
そもそも僕と肇君は、2012年に彼が東京で開講した写真のワークショップを僕が受講したことで初めて出会っています。そのときにはもうすでに彼は海外でも評価されて、色んな場所で精力的に活動していました。いまでも僕のなかで大切な言葉として覚えているんですけど、彼はそのときに「写真を残していきたい」と言っていました。肇君はあまり覚えていないそうですが、僕は感銘を受けました。「写真を残すってどういうことだろう」って。意識的かどうかはわかりませんが、彼は写真を残すために自分が作品を作るんだと、写真を残すためにどういったことができるのかを論理的に考えながら作家活動をやっている。とにかく僕は彼の言う「残す」ってどういうことだろう、と感銘を受けて、そこから付き合いが始まりました。
木村:写真を始める前は大学で建築を専攻していました。2000年に入学、4年後に卒業して、その後1年間だけ写真の専門学校に行っていました。建築を専攻しながらも、ダメ学生で卒業も危うかったですが、その後いろいろあって写真をやりたい、さらにドキュメンタリーベースの作品を作りたいと思うようになりました。ただ、撮るものが確立されていなかったので、まずはニューヨークにあるICTで学びたいと思っていました。でも学費が高すぎてかなわず、しかたなく東京の専門学校、それも夜間に一年間だけ通いました。さっきも言ったようにそれまでは撮りたいものがなかったのですが、その期間でたまたま撮りたいものを見つけて、新聞社とかに就職しようと思っていたのをやめて、自分のやりたいことをやってみようと。そのテーマっていうのがマタギでした。

ちょっと上の世代の方だとマタギやサンカの存在を知っている方もいらっしゃると思いますが、基本的には「なにそれ?」という反応です。一言でいうと、狩猟、採集でお金を使わずに生活している人たちのことです。
当時はそうやって暮らしている人たちが日本にまだいるんじゃないかと思っていました。なぜそう思ったかというと、大学時代、建築の分野ですが、コミュニティデザインや田舎の文化の成り立ち調査に関わっていました。それが新潟の佐渡島だったんです。その文化を4年生のころ調べていました。郷土資料館の図書館で資料を見ていたら、江戸時代くらいの人たちかなと思うような写真が出てきたのですが、よく見てみたら1980年代くらいだったんです。
つい2、30年前までこんな生活を新潟の内地でしている人たちがいたんだって、そこからずっと気になり始めました。大学の頃から休学して中国とかのアジア圏をバックパッカーみたいなこともしていて、民俗学的なことが好きだったので、日本でもこういう人たちがいるんだと。大学の頃にそういうふうに関心があって、専門学校を出ても、引き続きやりたいと思って色々リサーチしました。そしたら恐らく新潟にそういう暮らしをしている方々がいるんじゃないかということで実際にその人たちと出会いました。
もともとは熊谷達也さんという方の『相剋の森』という本の舞台になっているところなんです。それもあって行ってみたいと思っていました。で、当時お金がなかったので千葉県から自転車で行きました。

吉田:えっ! なんとなくの検討はついていたけど、誰かにアポイントメントを取ったわけでもなく自転車で行って、着いてから具体的な場所をあたっていった、という感じですか?
木村:ほんとにそうです。「どこどこ村のだれだれ知っていますか?」みたいな。でもそれは現実世界の話じゃなくて、『相剋の森』の登場人物なんですよ。だからフィクション入っているので「この物語でモデルになっている人知りませんか?」とか。そしたら知ってるみたいな人が何人かいたので、突き止めて。もうストーカーですね。
吉田:すごい!そこから関係性を築いていくんですよね。そのときはまだカメラのキャリアを本格的に築いてって考えるようなタイミングでもなかったんですよね?
木村:はい。技術的なことは学んでいたんですけど、長いタームでひとつのプロジェクトをやるという概念もなくて。単純にその人たちに会って一緒に暮らしたいとか、長い時間取材してみたいとか、ほんとそれくらいでした。本を作ることも考えていなかったし、どうやってアウトプットするのかすら何も考えていませんでした。
吉田:じゃあもうとにかく会ってみたいというので最初に行って、そこからは通い出したということですか?
木村:そうです。この『マタギ』という作品を最初に出版したのがちょうど吉田さんとお会いしたのと同じ2012年で、たぶんこれはもう絶版なのかな。タイトルはマタギではなく『谺(こだま)』という写真集なんですけど。

2007年から最終的には2013年までかかったので、6、7年くらいは撮っていました。このなかで自分が何をもってプロジェクトを進めているのかっていうのをずっと考えていて、2、3年撮って、関係性もできて、作品としてもある程度できあがってきたときに、日本の色んなメディアやギャラリーに見せたんです。でも2、3枚見て、「古いから無理」って。「なんでカラーじゃないの?」とか「なんでふわっとしてないの?パキッとしてるの?」とか。
でも、僕のなかで「良いものというのは何か」ということについてはプロジェクトをやる前から考えていて、それこそ写真をやろうと思ったときに、自分に課していたトレーニングがありました。つまり一日一回は写真以外でも絵画なり映画なりの展覧会を見て、それの何が良くて何が良くなかったのかを毎日列挙していたんです。そうすると共通して自分が良いと思うもの、共通して自分が悪いと思うものが洗い出されるじゃないですか。
その結果、自分が本当に良いと思ったものの共通項が3つありました。(1)時間をかけること、(2)被写体と関係性を作ること、(3)そしてそのうえでフレキシブルになることです。それらのうえで表現は成りたつんじゃないかと思っていたんです。もっというと、ただ時間をかけるのではだめで、無理なく自然に関係性を築いていく。ちゃんとした土台があってはじめてデザインができるという意味で、それは建築でも同じです。
そんなことをベースにして『マタギ』を作っていたんですけど、見せても門前払いというか、そもそも内容を見てすらもらえなかった。それでちょっとやけくそになった部分もあって、2010年か11年くらいに一回写真を辞めました。で、海外の映像制作の会社に1年半から2年弱いたんですけど、当時、自分が撮った写真を持っていたんですよ。ヨーロッパとカナダにいたんですけど、会社が休みのときに社用車を使って写真の営業に回りました。そしたらたまたまフランスのギャラリーやメディアの人たちが良いって言ってくださって救われたというか。今思えばですけどね。でもそれがなかったら本当に辞めていたと思います。
吉田:いまでも活動のベースは向こうのことが多いと思います。それというのはこの作品が海外で評価されたことが契機になって広がっていったからなんですかね。
木村:そうですね。
吉田:実はこの『マタギ』という作品は今回の『嘘の家族』にも強く影響を与えているので、『マタギ』でどんな人と関係性を築いてどんな人たちを撮ったのかを頭に入れたうえでこの後の話を聞いてもらいたいと思います。5、6年くらいをかけて2012年に作品として出版されたわけですよね。その後の展開は?
木村:自分のなかでは写真に対して二つの方向性がありました。よりクラフトライクなものを作りたいという欲望がひとつ。実際に『scrap book』という写真集を2015年に出版しました。

もうひとつは『マタギ』のプロジェクトは2013、14年で大体が終わっているんですけど、そのあとも関係性は続いていて、熊討ちのときなんかは写真も撮らないのに見に行ったりしていました。
そもそもマタギの人を撮ったきっかけというのは僕が千葉の柏市に生まれ育って、正直言うと中途半端な場所なんですよ。田んぼはあるけど山はない、中途半端な都会。ヤンキーもいる。そんな生まれ育った環境が嫌で、家族との関係ももちろんあるんですけど、小さいときから早く出たいとずっと思っていました。その反動からもっと山深いところで生活している人に興味の対象が向いていったというのは、今思えばそういうことなのかなと。
写真を撮り始めたころは写真で食べられていなかったので東京でアルバイトしていました。寿司屋のデリバリーです。新宿区と千代田区あたりをずっと巡っていて、そのなかにいつも注文してくれる身寄りのないおじいちゃんがいました。カリエスを患っていて鼻にチューブを差しているんですけどすごく元気で、僕がお寿司を渡すといつも挨拶してくれて。個人的に彼に興味を持ちました。
マタギを撮るなかで出会うご老人が元気な一方で、新宿区でデリバリーのお寿司を食べながら暮らしているおじいちゃんもいる。同じ年代とは思えない対照的な暮らしをしているっていうのはどういうことなんだろうと。そうして、マタギから逆に今度は都会に住んでいる人たちに興味が出てきました。そのおじいちゃんのことを2、3年撮っていたんですけど亡くなってしまいました。それで葬儀をして、そのあとに自分の父親が癌で亡くなるんですけど、その父親を見たときに都会で暮らしてるおじいちゃんに見えたんですよ。だから結局マタギというのは自分の外側の世界ですけど、ルーツは自分の内側にあって、そこから高齢者の生活に興味が湧きだして、僕の母親は高校生のときに亡くなっているんですけど、よくよく考えたら父は一人暮らしの老人だったんだよなと思って。両親が高齢出産だったので41歳くらいのときに僕が産まれました。それで自分の父親がどういう暮らしをしてるのかっていうのに興味がありました。なぜかというと、僕は写真を撮り始めてからは家が嫌だったので飛び出して帰っていなかったので、父がどういう暮らしをしているのかを知らなかったんです。でもマタギの作品を通じて帰ってきた。それがつまり自分の家族というテーマに興味を持ったトリガーというか、もしかしたらもっと細かくはあったと思うんですけど、写真を撮り始めたのはそれがきっかけです。
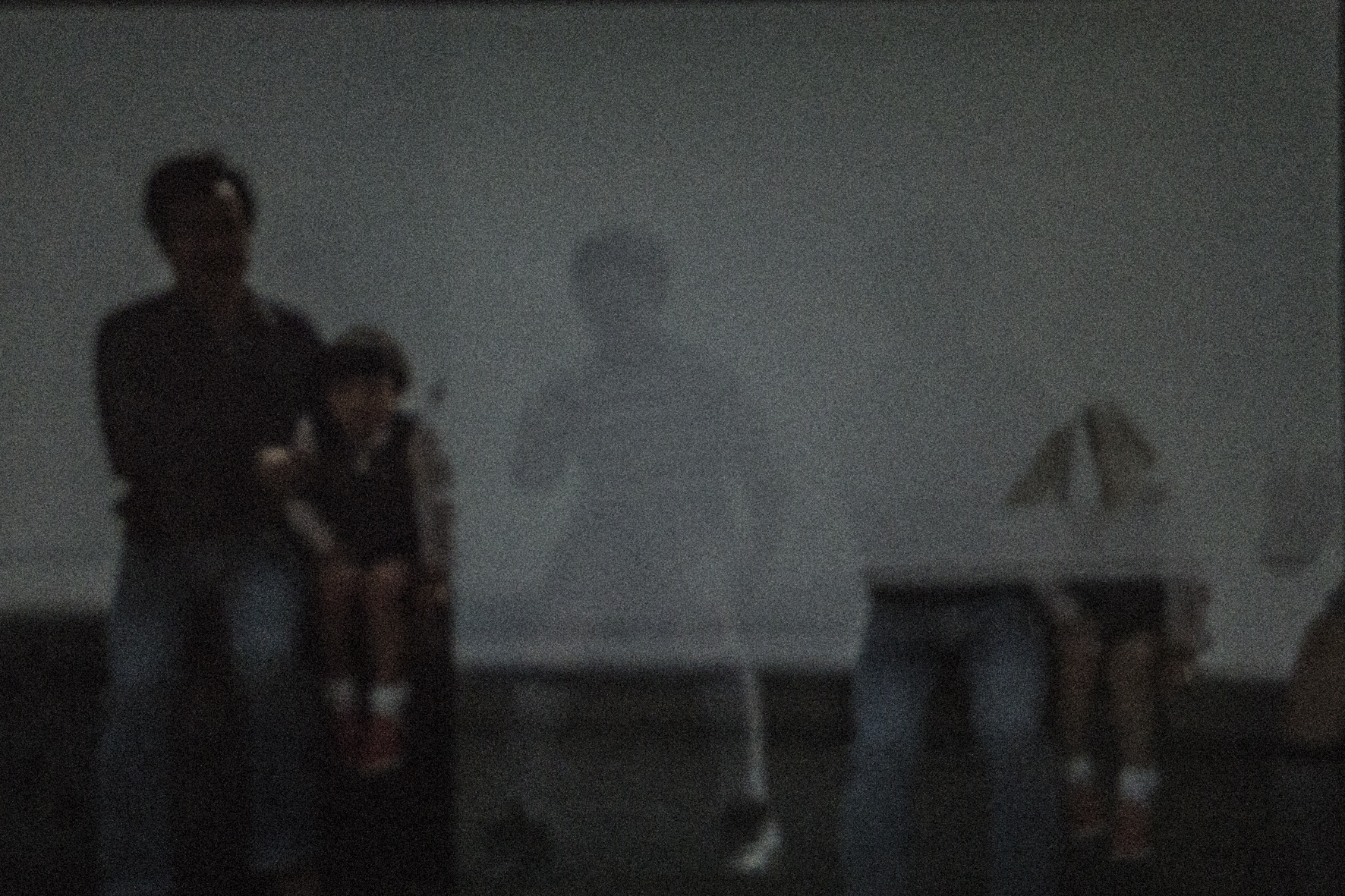
吉田:今の話を聞いていて僕も作品を作るからすごくよくわかるんですけど、写真って自分の外側にあるものしか撮れないじゃないですか。それを料理して、向き合って、作品にしていくと。でも作品って、結局内面の問題だったりとか、自分が気づいていないところを如実に反映している鏡みたいなものだと思うんですよ。作品としてでてきて初めて、自分ってこういうことに気づいていたんだな、こういうことを欲望していたんだなっていうのに気づかされることってけっこうあります。作品によって初めて自分の足元が照らされるみたいな。いまの肇君の話でも、マタギを通して自分のルーツである家族に行くというのはまさにそういうことかなって。作品と向き合うと次の作品に派生していくじゃないですか。足元が照らされるような感覚はとても共感します。
でもお父さんやお母さん、家族に対して肇君は強いコンプレックスというか、明確に嫌いだった、離れたかったと小学生の頃から思っていたと本でも書いてあるんですけど、なぜそこまで嫌いと言えるのかなって。
木村:嫌いっていうのも色んな性格があると思うんですよ。僕の場合は家が貧乏だったというわけでもない。両親が犯罪者だったわけでもない。父がサラリーマンで母が主婦で、何も不満がないような平均的なうちだったと思います。この本にも書いていますけど、僕は母から受けた影響がすごく強くて、それは、僕が家に帰ると父はサラリーマンだから家にいないけど、母は主婦だからいた。いま思い出すと母はすごく厳しかったです。いわゆる良い成績をとって、良い学校に行ってそこを出て、良い会社に入れば、幸せな人生が待っていると口ずっぱく言われていました。実際母も優秀な学校を出ていて、文武両道でやってきたわけですよ。でも小さいながらに父と母の生活を見ていて幸せだと思えなかった。一方で母はその生活を勧めてくる。
僕のなかで母は厳しかったけど唯一何かを教えてくれる存在でした。母の教えがすべてだった。だから母がそういうんだったらそうなんだなって。でもいつからか「本当にそうなのか?」と思い始めました。だからと言って「嫌い」という感情があったわけではなく、疑いを持ち始めたというか。ドラスティックにヒステリーを起こすわけじゃないんだけれども、もしかしたら母は僕に嘘をついているんじゃないかと思ったことがたくさんありました。例えば年齢を詐称するとか(笑)。僕が小6くらいのとき、母の年齢を20歳だと思っていたんですよ。でも林間学校かなんかのタイミングで母の保険証を提出しなきゃいけないことがあって、受け取ってみたら昭和16年生まれって書いてあるんですよ。20歳じゃない!みたいな(笑)。嘘ついてるって。40、50代のおばあさんじゃんってショックを受けました。
父と母はあまり仲良くなかったんですよ。父は酒もたばこもしますし、家でよくふたりで喧嘩していました。事あるごとに「離婚する」「家出ていく」って。僕が小3、4くらいのときに「あなたはどっちについてくるの?」って。「別れるからどっちか決めなさい」って。僕は父が嫌だったのでお母さんといることを選びました。

自分のなかで理想の家族像があったんですよ。例えば小学生のときに思っていたのは両親どちらも20歳でキラキラしている(笑)。でもそれが段々ほころびを見せ始めて、「なんか20歳ではないな」「ずっと喧嘩しているし皿も投げてるしおかしいな」と。母が言うことには従ってはいましたけど、実際の家族が理想としていた家族ではないことはわかってきます。そのことを友だちに言えればよかったんですが、僕は逆に「トレンディドラマのような良い家族だ」と言っていた。でもその嘘がバレるので友だちを家に呼べませんでした。じゃあなぜそのとき友だちに本当のことを言えなかったのかを今振り返って考えると、ずっと母から言われていた、良い学校から良い会社に就職するのが良い人生というのが幸せな家族像として刷り込まれていたからだと思うんですね。でもそれが違うというのもわかってきてしまった。この話って程度の差はあれど色んな人が同じような経験をしているんじゃないですか。
吉田:うちの実家は中華料理屋をやっていたのですが、ずっと「サラリーマン家庭の子どもに産まれたかった」と思っていました。自分がいまいる環境とは違うものを求めてしまうというか。なぜか安心できなかったというのは似ている気がします。
木村:おっしゃる通りです。家にいて安心できるのって父がいないときなんですよ。父がいると喧嘩になるので。加えて自分が良い成績をとっているとき。そのときは母からも文句を言われない。それが安住のシチュエーションです。今思えば幼いながらにしてよくやっていたなと(笑)。現在の目線でなぜ自分が家族に執着しているかを考えるとそういった部分に行きつくかなと。
『Snowflakes Dog man』というのは亡くなった父が飼っていた犬の話です。これは父が亡くなる前と亡くなった後で本が2冊に分かれていて、それぞれの記憶が合わされるかどうかをテーマにしています。自分は父が嫌いだったんですけど、父が亡くなるってわかってからは彼を撮り始めたのは、その人を理解していくっていうのと、亡くなったあとは話すことができないじゃないですか。撮り始めたのは、父が癌にかかってから、亡くなる1か月半くらい前からですが、大事な人が亡くなったときにそのことを人はどう理解するのか、どう咀嚼していくのかということに興味が湧き出しました。そういう本なんです。

吉田:なるほど。自分自身を理解するための本、父がいなくなったという現実を自分自身がどう解釈して咀嚼していくのかっていう本なんですね。
木村:そうです。両親、祖父や祖母、あるいは大切な友人が亡くなる、もしくは音信不通の状態になったとき、そのことをどうやって受け入れるのか。そのことについての本なんです。さっきの話に戻りますけど、それって一番外側です。関係性も築いていて時間もかけているんですけど、できあがった結果というのがひとつの作品になっていて、ある意味そのプロセスも描いてはいますが限りなく外側に近いものです。だから母親が年齢を偽っていたとか両親が喧嘩をしていたっていうのは、この本では描かれていないんですよ。そこは端折って、ひとりの男性と彼が飼っていた犬っていうのに特化した話。だけど本当は「なぜ亡くなった父を撮るのか」「なぜ出版を通して父の死を公衆の面前で言わなければいけないのか」といった理由はもっと深いところにあるんじゃないか。そんなことを出版したあとに色々と考えました。もちろん作っている最中にも考えてはいましたが、時間がたてばたつほど冷静に考えられるようになります。やっぱり印刷室にいると感情的になりますから。そういった意味で表面には出てこないコアの部分を今回の『嘘の家族』で……
(後半に続く)

