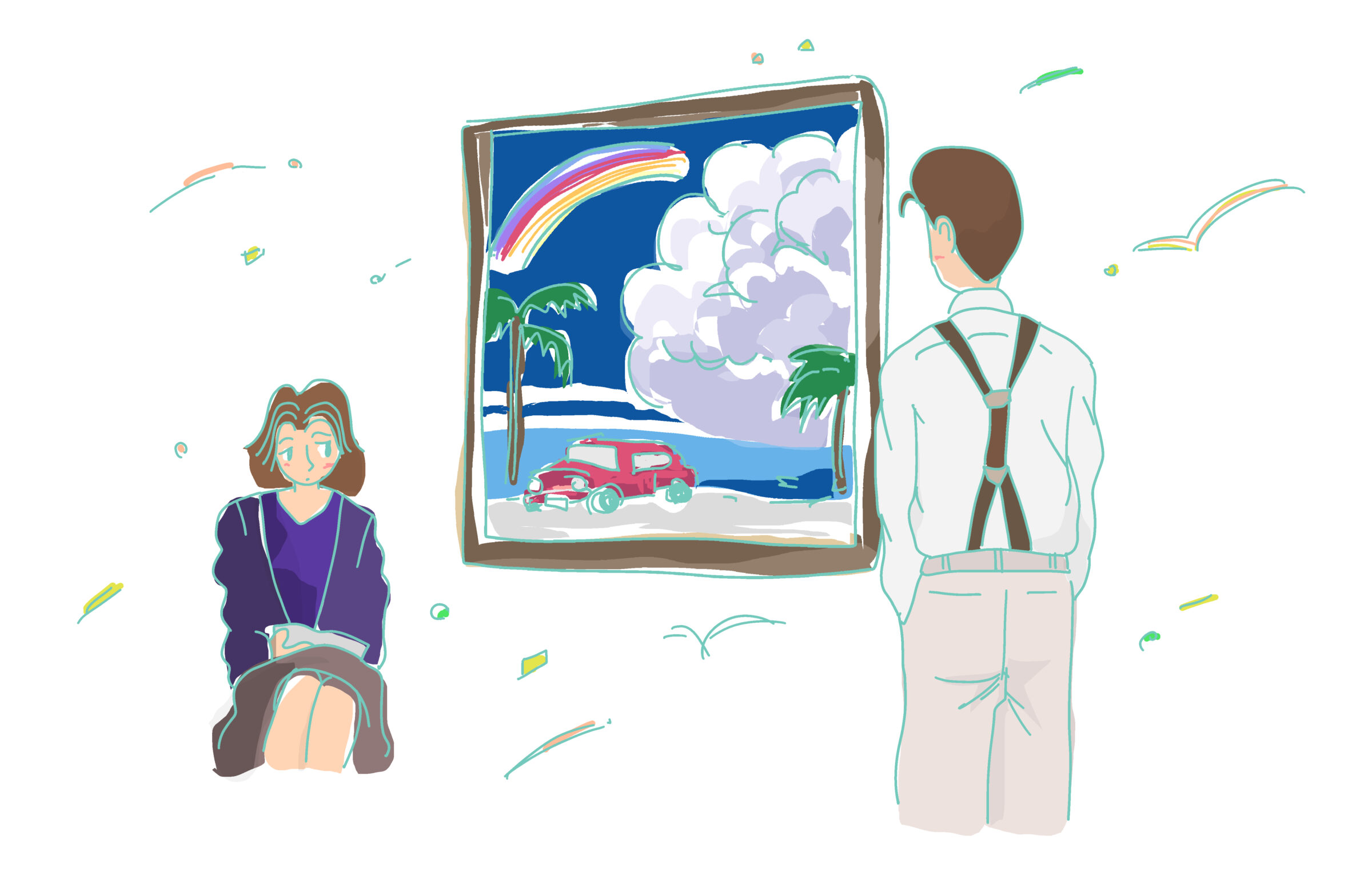最近聞いた名前
なまえのこと
漫画ナマエミョウジ文フィクショナガシン
監視員といえば高いところから見守っているプールの監視員が思いつくが、美術館の展覧会にも監視員がいて、観客が展示作品に触ったり、踏んづけたりしないよう注意を払っている。
プールの監視員は溺れたりしてないか人間の安全を見守る仕事で、展覧会の監視員は作品の安全を維持するのが仕事であり、役目は違うが、予想外の動きをする人間の行動を「監視」するという意味では同じである(後者には見守るという意味のある「看視」をあてる場合もある)。求人サイトを見てみると、展覧会にいる監視員とプールにいる監視員を派遣している会社は同じだったりする。
先日広島の美術館でワークショップの仕事があり、監視員の方々に話を聞く機会もあったのだが、大変興味深かった。広い展覧会場を1人で監視するわけにはいかない。数名でローテーションしながら観客を見守っているのであるが、何か怪しげな人影があるとインカムで共有するそうである。
「青のシャツをお召しの50前後と思われる男性のお客様、飴玉らしきものをなめている可能性あり。今、そちらのフロアに行きました」
「了解」
という具合である。
「先ほどの飴玉、青シャツ、50前後の男性のお客様、確認しました。飴玉は確認できず。こちらの勘違いか、飴玉もう舐め終えた可能性あり。今、次のフロアに行きました」
「はい、了解です。あ、来ました。口もと怪しい動きしてます。もぐもぐしてます。足早に次のフロアに行きました」
「了解です。飴玉でもぐもぐは不自然なので、ガムかもしれません。いや、ハイチュウの可能性も捨てきれず」
と、まあ、会話自体は私の創作だが、飴玉可能性おじさんの情報共有は実際にあったとのことである。口もとの動きで飴玉の可能性を読み取っているのがすごい。監視員の方に我々は細部まで見られているのである。
別に飴玉くらいいいじゃないか、と思うかもしれないが、展示室内は飲食禁止であり、万が一のこともあり、お声はかけないが、注目しているとのことであった。万が一とはどういうことかというと、咳き込んで、吐き出して、それが作品にベチャッとついちゃうとかである。そんなことはめったにない。めったにないけれども、飴玉を舐めている観客が1万人いたら1人ぐらいはプーッと吐き出してしまうことはありそうなことであり、注意深く見ておく必要があるわけだ。
私の経験では、ガムや飴玉ではないけれども、ボールペンでメモを書いていたら、監視の人がスーッと近づいてきて「これを使っていただければ」と、申し訳なさそうに鉛筆を差し出すということが過去何度もあった。ボールペンのどこがいけないかというと、インクがピューッと出て作品についてしまう可能性があるからだそうである。美術館には、インクがピューッと出てる的な、そういう禁止マークを示している場合もある。
安物の万年筆じゃあるまいし、ボールペンのインクがピューッと出るなど日常でも見たことがないが、規則で決まっているから監視員としては注意せざるをえない。ピューッとインクが出るなど非現実的であると監視員諸君も、もちろん思っているのだろう、そのため、ややすまなそうに、そっと鉛筆を貸してくれるのではないかと推察する。
それにしても遠くからよくボールペンとわかったものだと思う。こちらとしては、ボールペンの使用がダメなのは知っているから、バレないように手元を隠しながら書こうとしていたわけであるが、にもかかわらず、そんな私を発見し、近寄ってきて「申し訳ありませんが」と言いながら鉛筆をサッと渡したのである。見られていたことに感銘に近い何かを感じなくもない。コソコソしていたことでかえって目立ってしまったのかもしれないが、いずれにせよ、監視とは非常に繊細な仕事だと思ったのである(今は鉛筆を持っています)。
私が仕事でうかがったその美術館では、監視の人に混じって、というかアートナビゲーターが監視員も兼ねていて常時会場内にいる。バッジをつけていて、一目瞭然に判別できるようになっており、アートナビという名前だそうだ。今回初めて知ったが、非常にいい仕組みであると思う。
アートナビ監視員は先述のように派遣会社からやってくるのであるが、展覧会に合わせてその都度、美術館の学芸員からレクチャーを受けており知識を身につけている。観客にとっては、気軽に聞けるのでありがたい存在である。声をかけてくれたら答えるが、あまり答えすぎないように気をつけているという。観客自身が考える余地を残しておきたいからである。人を見ながら、その人に合わせるように話すらしい。ロクに作品を見ないで去っていく観客に、もうちょっと長く見ていてほしかったな、と思いながら観客の背中を見つめることもあるそうだ。
しかしながらどの美術館の監視員もアートナビゲーターを兼ねているわけではない。これは広島じゃなくて別の美術館のことでしかもだいぶ前のことであるが、作品について質問したら、「学芸に連絡しますッ!」とわざわざ学芸員に内線で電話し、その学芸員がエレベーターで降りてきてこちらへ駆けつけ、「ご質問は」みたいなことがあってこれはちょっと大げさというか、「悪かったなあ」と恐縮したものである。
これも別の美術館であるが、やはりうっかり監視の人に質問したら、「ハッ! 学芸室に伝えます!」という感じで同じ展開になり「今、不在ですので、後ほど電話かメールを差し上げます!」と言われた。丁寧な対応にありがたいと感謝しながらも、やはりちょっと気が重い。恥ずかしながらそれほど大した質問でもなく(作品に使われているこの木はどこから持ってきたのか、みたいな程度)、自分が情けない、そんな気持ちになったものである。観客のニーズに応えたいという熱い気持ちは素晴らしいが。
逆に、こんなこともあった。金沢のとある未来を感じさせる名前の美術館だったが、近くにたまたま監視員の方がいたので、またしてもうっかり質問したら、「私に聞かないでくださいッ!」と投げ捨てるように言われ、サッと離れていった。申し訳ない思いがしたが、やや異様な対応ではなかったかと思う(聞いた私も悪いがびっくりした)。
ところで、一般的に監視員は存在感を消す。消そうとするが人間という物質的な存在である限り、どこか具体的な場所を占有せざるをえない。椅子があり、ひざ掛けやファイル、観客に貸し出すための鉛筆などがあったりする。会場のすみっこのことも多い。
しかし会場のすみっこにも絵がかかっている場合が割とあって、その絵を見ようと近づくと、そこにいた監視員が、スッと、姿を消すかのようにさりげなく遠ざかる。
鑑賞の邪魔をしないよう配慮してくれているわけであるが、私は自意識過剰であり、スッと離れられたことに少し傷つかざるをえない。監視員のせいではない。せいではないのだが、「私から去っていった」ことが気になり、そのため心拍数が上がらざるをえない。さらに、背後から見られているのかもしれないという自意識も発動し、背中がかゆくならざるをえない。だからと言って、監視の人が近くにいたままだったら余計に緊張してしまい、心拍数はやはり上昇せざるをえないのである。私は、そのため、監視の人の椅子の近くのいわゆるすみっこ作品に関しては「見たふり」だけして早々に切り上げすたこら立ち去ってしまうことがしばしばなのである。
繰り返すが監視の人のせいではない。私は、いざ、監視員がいない世界に住むことになったら、展覧会に来ても、素直に「寂しい」と感じるだろう。
人件費が高騰し、展覧会の予算を圧迫する中では、いずれ監視もAI搭載ロボットが担当するようになるかもしれない。アートナビもAIが自動音声で、バッジをつけたCG動画で、質問に答えるかもしれない。未来の観客は、「昔は生身の人間が会場にいて、監視してたんだってね」とか話すことになるかもしれない。生身の監視員がいることで生じるちょっと気まずい「あの感じ」、その空気はどこにも保存されない。消えてしまう。レビューにも、図録にも、監視員さんの姿は残らない。観客の、ちょっとした記憶の中にしか残らない。
シティポップと呼ばれる日本発の80年代の音楽が、2020年前後から、海外で面白がられ、逆輸入された形で今度は日本で、ブームになった。いきなり話が飛んだように思うかもしれないが、その通りだ。だが、時代の「空気」の保存のことを考えたらこうなった。音楽は、機材の変遷やスタジオの雰囲気、その時の、その年齢でのミュージシャンの腕前や歌声が、レコードとして保存されるので、シティポップサウンドの「あの感じ」は当時のもので、今、それを真似しても、「あの空気」にはならない。同じミュージシャンが当時の曲をやっても今の空気になってしまうだろう。機材も声も変化しているし、風貌も(年齢を重ねて)だいぶ変わっている。往年のファンは、わずかに残った当時の面影を見て、喜ぶのである。
当時シティポップって言ってたっけな、と思ったが、柴崎祐二編著『シティポップとは何か』(2022/河出書房新社)を読むと、70年代後半に生まれた「シティポップス」が原型だったようだ。「ス」が付いた状態で、同時代のサウンドを指す宣伝文句として生まれたそうだが、その名の通り都会的で、労働よりも消費が優位にあるような、人々が政治から遠くにあるようなそんな世界をシティポップスは奏でた。
シティポップスは80年代後半から90年代に一度下火になり(渋谷系、そしてJ-POPの時代になり)、近年、再び火がつき、その影響を受けた新世代のミュージシャンの作品も含めた名前として2000年前後に「シティポップ」になったという。つまり、シティポップという名前は(シティポップスとは異なり)、後から付けられたジャンル名というわけだ。
ちなみに『シティポップとは何か』は、その前史からピーク、その後の広がりも含めて複雑な歴史がわかりやすく整理されている。音楽の流行現象の話題に終わらず、ポストモダンの行く末を捉えた文化論としてもまとまっていて面白かった。
よく言われる「シティポップ=バブル期の音楽」という捉え方は間違いで、バブル景気以前の80年代前半に全盛期があったと編著者の柴崎祐二が指摘している箇所は重要だ。「シティポップが内包していた豊かさや舶来文化への憧れ」は、バブルの狂乱の予兆であり、バブル期にはむしろ失速している、と。シティポップとは、一瞬だけ垣間見ることが可能だったフィクショナルな風景ではないかというわけだ。
シティポップの全盛期だった84年に平中悠一は、小説『“She’s Rain”シーズ・レイン』で文藝賞を受賞しデビューした。中編ほどの軽い、カジュアルな単行本として、原田治のお洒落な装画をまとって翌年、刊行された(そういえば83年デビューの浅田彰の2冊目『逃走論 スキゾキッズの冒険』[筑摩書房/1984]も原田治である)。
続く『“Early Autumn”アーリィ・オータム』(河出書房新社/1986)でも都市の空気をたっぷり吸い込んだボーイ・ミーツ・ガール、そのキラキラした日常を「文字だけ」で描き出してみせた。映像が見えるようで見えない、ストーリーに魅せられるというよりもそこで繰り広げられる空気感、言葉の数々が魅力で、例えば、
ったく。
なんていう主人公の心内語があり、現代文学の語り手が発する感情としては見たことのないもので驚いた。
他にも、改行の多用や、あえて語り手のセリフにのみカギカッコを使用させない会話の表記の仕方、「女のコ」というこれまた文字でしか表現できない書き方が、ひ弱そうに見せながらその実、図太いたくましさを感じさせた。
私が平中悠一を読み出したのは、彼のデビューから数年を経た80年代の終わり近く、十代後半あたりだった。主人公達と同じくらいの年齢だったわけだが、その生き方には共感はちっともできなかった。
だが、読んでいた。なぜなら、「いや、それでいい、こっちはこっちで勝手にやるから」と小説が言っているように感じられて、それが小気味よかったから。勝手にやってろ、と、こちらもツッコミながらつい読んでしまっていた。文字だけなのに何か「生きている」というか、声が聞こえた。小説という形式の中でしか聞けない声がしたように思った。
ただし作家の年齢が上がるにつれて息苦しくなり(読者が)、作品のページ数も増え、本が物理的に重たくなり、その分だけ、作品も失速していったように私は思っていた。『麗しのUS』(河出書房新社/1992)、『ゴー・ゴー・ガールズ(⇔スウィング・アウト・ボーイズ)』(河出書房新社/1995)あたりまでは熱心に読んでいたが、それ以降は追っていなかった。平中悠一の名前もいつしか見なくなり、消えたのかと思い、心配もしていたが(個人的には面識はないが)、今年復活した。
平中悠一は『シティポップ短篇集』(田端書店/2024)というアンソロジーを編纂したのである(実はもう1冊、新刊の単著を同時刊行しているが、これについてはまた今度紹介したい)。消えたと思っていたのは私の完全な勘違いで、彼は書いていた(パリに留学して文学研究、翻訳をしていた)。私のような、かつての読者の視界から見えなくなっていただけ、物書きとしての時間は持続していたのである。シティポップのミュージシャンが、そのジャンル分けとは無縁に、年を取ってもなお「自分の音楽」を弾き続けているように。
『シティポップ短篇集』は、80年代に発表された短編を集めたもので、もちろん当時からそんな名前で呼ばれてなんかなかった。今、シティポップと呼ばれる音楽ジャンルがブームだからそれになぞらえて、というか、あやかって、同時代の「都会的」な短編群を、そのシティポップという考え方で捉えてみたらまさにぴったりだった、ということだ。80年代の小説群の後、90年代からはJ文学と呼ばれる一群の新しい作家達が出現するが、シティポップからJ-popへの流れとの平行性があるかもしれない(とはいえ、ずっと以前から同じような人選でアンソロジーを構想していたという)。
片岡義男、川西蘭、銀色夏生、沢野ひとし、原田宗典、山川健一、そして編者平中悠一というラインナップで、「文学」の非主流派というべきだろうが、驚いたことにどれも今読んでも面白い。携帯が1台も存在しない世界だが、まるでこっちが本当のあるべき今の姿だとでもいうような顔で登場人物達が振る舞っている。遠慮というものをみんな知らないのだ。
平中悠一の「かぼちゃ、come on!」は、まずこのタイトルが、今の時代の読者からは「ない」と言われるにちがいない。不真面目で、バカバカしく、意味不明だから。だが、この作品の語り手が今の文芸誌の目次に並ぶタイトルを見たら「ったく、ったく」と言うだろう。「かぼちゃ、come on!」は今回、初めて読んだが、時を経て、読者の私も歳をとったというのに、平中悠一作品を読むその感覚は当時とまったく変わらなかった。相変わらずのボーイズ・アンド・ガールズ、恋に浮かれたセリフの数々は、誰にも忖度しておらず、楽しそうだ、そう思った。小説の方が、こっちはこっちで勝手にやるから、と言ってるようだ、そう思った。勝手にやってろ、と、そう思った。そう、この感じ。
変化があるとしたら、これは他の収録作を読みながらも感じたことだけど、小説の中から、「君、なんか不自由してない? 遠慮してない?」って問われているような気がしてきたことだ。80年代小説からの、現代へのメッセージというか……
いや、同時にこんな声も聞こえてくる。
でもさ、ほんとにそう? メッセージなんて受け取っちゃうなんて、よほど今の君、弱ってるんじゃないの。ったく!