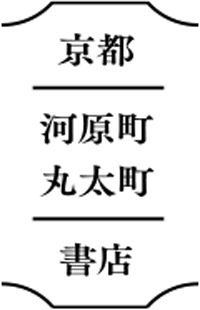七〇にしてふたたび童貞
過日、「ポメラ」なるものを衝動買いした。ひと言でいえばポケットサイズのワープロ、テキスト入力に特化したガジェットだ。パソコンで原稿を書いていると、ついつい調べ物をする流れでネットサーフィンがはじまり、気がつけば、フライデー襲撃事件後のビートたけしの記者会見をぼーっと観ていたり、中古レコード屋のサイトで欲しくもないレコードを片っ端から試聴していたりする。
そういったノイズをシャットアウトし、ストイックに原稿やキャプション書きに専念するため、意気揚々と買ったばかりのポメラ持参でカフェを訪れた直後、何度目かのコロナウィルス感染拡大で外出機会が減った。それ以来、二年近く触れることもなく引き出しにしまわれたままになっている。次に手に取る日は来るのだろうか。思えばICレコーダーみたいなサイズのデジカメを購入したときも、『E.T.』みたいなフォルムのスチームアイロンを買ったときも、数度使っただけでお蔵入りとなった。
自分には「ライフハック」なる言葉は縁遠い。箸が使えて自転車に乗れるようになったあたりで、いまの生き方はほぼ完成していたような気がする。十代の頃には存在しなかったパソコンもスマートフォンも仕事のあり方を一変させてしまったが、生活上はできるだけ遠ざけるように生きてきた。この先、わが習慣を一変させるような、しがみつきたくなるようなガジェットは現れるのだろうか。
飲んだくれで女たらし、あらゆる権威に与することなく、日々の労働とギャンブルに明け暮れながら、リトルマガジンというフィールドを主戦場に執筆を続けた無頼派作家。そんなパブリックイメージとは裏腹に、チャールズ・ブコウスキーは、長年愛用したタイプライターから当時まだ目新しかったマッキントッシュに乗り換えて創作に没頭した。昔気質の編集者たちからは、タイプライターを捨てた作家の姿に対して拒否反応もあったらしい。
彼にマックの購入を勧めたのは、ブラック・スパロウ・プレスの主催者ジョン・マーティン。ブコウスキーの作品を早くから評価し、小規模ながら多数の詩集を刊行、最大の理解者として死後も膨大な遺稿をまとめ、出版を続けた。おそらくこの助言は、思いつくままに書き飛ばされるテキストを、散逸を避けてデータ化し、アーカイブとして扱いやすくするための判断だったのだろう。事実、コンピューターを駆使し、悪戦苦闘しながら徒然なるままに晩年の日々を記録した 『死をポケットに入れて』がブラック・スパロウ・プレスから刊行されている。挿絵を描いたのはアンダーグラウンド・コミックスの帝王、ロバート・クラム。このコンビは早くも一九八〇年代の初頭、同社から刊行された詩集で実現している。同じく自らの性癖をさらけ出し、きれいごとを一切排した作品をアンダーグラウンド・プレスに発表し続けたクラムは、ブコウスキーに多大なる共感を寄せていたのだろう。
同書によれば一九九〇年の秋に発売されたばかりの“マッキントッシュⅡsi”を、早くも翌年一月に購入。当時の小売参考価格は二九九九ドル。ブコウスキー自身、三十数年に及ぶ競馬生活での勝ち越しがこの時点で五千ドル程度だったと言うから、決して安くはない買い物だった。
”青い閃光”に書きかけの原稿を奪い去られ、時折現れる爆弾マークに怯え、強迫観念からレーザープリンター用紙を買い占め、飼い猫に小便をかけられないよう使用後はタオルをかぶせた。彼のファンにとって、古希を迎えパソコン教室に通うブコウスキーの姿を想像するのは易しくはないだろう。
「再びおれは童貞だ。
七〇にして童貞。
マシンさま、ファックはごめんだ」
(「最初のコンピュータ・ポエム」原成吉訳)
こうまでしてマッキントッシュにしがみついたのは、彼が自らの死期を悟っていたからではないか。
「タイプライターで書くのは、泥の中を歩いているようなものだ。コンピューターは、アイス・スケートだ。猛烈な突風だ」
(『死をポケットに入れて』(中川五郎訳))
長年務めた郵便局を辞め、創作だけで生計を立てることができた遅咲きの作家ブコウスキーは、コンピューターを手に失われた時間を取り戻すかのように、猛烈に書き続けた。最後の長編小説となった『パルプ』では、「死の貴婦人」に依頼され、作家としての理想像であるセリーヌを探し求める探偵の姿を自身に重ね合わせている。死神に追いつかれぬよう、スピーディーに書き続けるためには、柄に合わないパソコン教室に通うことも辞さなかった。
雑然としたデスクに向かい、タバコ片手にしかめっ面でマッキントッシュに向かうブコウスキー。『死をポケットに入れて』(河出書房新社)のカバーに描かれたクラムによるポートレートには、自らの死期を予感しながらも、創作に打ち込み続ける作家の執念がみなぎっている。
- 初出:WEBマガジン「読読」